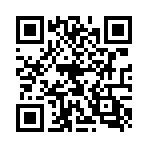2016(平成28)年は、日本磁器発祥 有田焼の創業400年を迎える
といった記念すべき年が待っています


そして気が付けば、また有田まで車を走らせていましたよ・・・。

まずは目的のひとつである九州陶磁文化館にて展示を見てさらいてから
柴コレも今回はまた違うモノに展示替えされていると思うので。。。
そちらは撮影OKなのでそれも楽しみにカメラの準備を整え いざ地下展示室へ


おっと!!やはり前回の品物とは顔ぶれが違ってますなぁ~・・・。
どれどれ。。。誰も人が居ないので落ち着いて撮れますな


今回はとりあえず器の雰囲気を楽しんで頂ければ、おてきちも嬉しいです


1630~1640年代
最初の頃は中国の焼物の影響を受けた製品が多く見られます。
1640年代になると赤や黄、緑の色彩を使った製品が登場します!!

流水に浮かぶ蓮の葉に2羽のセキレイが止まっています

その背後には風に棚引くオモダカが描かれています・・・。
1660~1670年代の製品のようですが、染付の濃淡が細やかですよねぇ

セキレイを2羽このようなポーズで配置するのは1660年代頃から流行し始め
1700年頃には鍋島藩窯の色絵の皿にも見られるそうですよ。
しかし上品な輪花の皿ですよねぇ・・・。

1670~1680年代
江戸時代で最も繊細で優美な焼物が作られた頃です。
素地が白く、形も正確で余白を十分に生かした構図が特徴のようです。

1690~1720年代
江戸時代で最も派手で豪華な焼物が作られた頃です。
白磁が見えないほどびっしりと文様を描くという特徴があります。

1750~1780年代
タコの足のような唐草文様がこの頃盛んに描かれます。
また染付や色絵に凹凸のある陽刻文様を使った表現が多く見られますね。

1790~1820年代
これまで見られなかった うぐいす色や明るい黄色の絵具が
この頃に登場します。
また染付では背景を呉須の藍で塗った白抜きの意匠が流行します。

これは柿右衛門の窯跡から出土した器のようですね


まだまだアップしたい写真はいっぱいあったのですが。。。
今回のところは このくらいにしておきますね!!

地図皿や舟形の器など目を愉しませてくれる斬新な図柄モノもあって
さすがこれだけのコレクションの数々は図録ではなく、器と醤油は生が1番

見応え以上に満足度が違いますねぇ~・・・。

これは江戸時代の食膳で 【料理早指南】 という1803年に刊行された
料理本を元に説明文が書かれていましたが。。。
本膳料理でも最高のものは五の膳まで揃うらしく
その膳立ては二汁七菜なんだとか・・・。
おてきちもお正月は、こんな感じに器を並べて祝い膳とシャレこもうかなぁ



器好きの方々、少しは喜んで頂けたでしょうか


なるべく多くの製品をアップしていけるように おてきちなりに努力致しますので
遠くて肥前までは、なかなか来られないという方々に一部でもお伝えする事が
今のおてきちの使命(任務)だと思っておりまする


これからも、乞うご期待下され!!
といった記念すべき年が待っています



そして気が付けば、また有田まで車を走らせていましたよ・・・。
まずは目的のひとつである九州陶磁文化館にて展示を見てさらいてから
柴コレも今回はまた違うモノに展示替えされていると思うので。。。
そちらは撮影OKなのでそれも楽しみにカメラの準備を整え いざ地下展示室へ


おっと!!やはり前回の品物とは顔ぶれが違ってますなぁ~・・・。
どれどれ。。。誰も人が居ないので落ち着いて撮れますな



今回はとりあえず器の雰囲気を楽しんで頂ければ、おてきちも嬉しいです


1630~1640年代

最初の頃は中国の焼物の影響を受けた製品が多く見られます。
1640年代になると赤や黄、緑の色彩を使った製品が登場します!!
流水に浮かぶ蓮の葉に2羽のセキレイが止まっています


その背後には風に棚引くオモダカが描かれています・・・。
1660~1670年代の製品のようですが、染付の濃淡が細やかですよねぇ


セキレイを2羽このようなポーズで配置するのは1660年代頃から流行し始め
1700年頃には鍋島藩窯の色絵の皿にも見られるそうですよ。
しかし上品な輪花の皿ですよねぇ・・・。
1670~1680年代

江戸時代で最も繊細で優美な焼物が作られた頃です。
素地が白く、形も正確で余白を十分に生かした構図が特徴のようです。
1690~1720年代

江戸時代で最も派手で豪華な焼物が作られた頃です。
白磁が見えないほどびっしりと文様を描くという特徴があります。
1750~1780年代

タコの足のような唐草文様がこの頃盛んに描かれます。
また染付や色絵に凹凸のある陽刻文様を使った表現が多く見られますね。
1790~1820年代

これまで見られなかった うぐいす色や明るい黄色の絵具が
この頃に登場します。
また染付では背景を呉須の藍で塗った白抜きの意匠が流行します。
これは柿右衛門の窯跡から出土した器のようですね



まだまだアップしたい写真はいっぱいあったのですが。。。
今回のところは このくらいにしておきますね!!
地図皿や舟形の器など目を愉しませてくれる斬新な図柄モノもあって
さすがこれだけのコレクションの数々は図録ではなく、器と醤油は生が1番


見応え以上に満足度が違いますねぇ~・・・。
これは江戸時代の食膳で 【料理早指南】 という1803年に刊行された
料理本を元に説明文が書かれていましたが。。。
本膳料理でも最高のものは五の膳まで揃うらしく
その膳立ては二汁七菜なんだとか・・・。
おてきちもお正月は、こんな感じに器を並べて祝い膳とシャレこもうかなぁ



器好きの方々、少しは喜んで頂けたでしょうか



なるべく多くの製品をアップしていけるように おてきちなりに努力致しますので
遠くて肥前までは、なかなか来られないという方々に一部でもお伝えする事が
今のおてきちの使命(任務)だと思っておりまする



これからも、乞うご期待下され!!