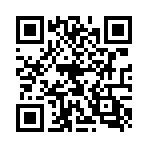古代より「海の道の要」として、また「日本の窓口」として
大海原の向こうにある異文化の国々と交流してきた長崎県の歴史は
人・食・建物など、どれをとってもそれは多彩で。。。
出合うモノ全てが鮮度が良く、またとても個性豊かなんですよねぇ


行って来ましたよん!!長崎老舗料亭 富貴楼



長崎と中国との接触は1600(慶長5)年に始まりました。
1633(寛永10)年、徳川家光は第1回の鎖国令を出し
中国の貿易船の入港許可は 長崎だけに限られたそうです

そして1689(元禄2)年に唐人屋敷が設けられ、それまで長崎市内に
散宿していた中国人は、現在の館内町の一区域に集まり住む事になりました。

中国人が長崎へ来て 唐人屋敷に移り住むまでの約80年の間
中国人が市中の町家に雑居することを、町宿(まちやど)と言ったらしく
その頃が最も市民と親密な交歓があった時代でもあるそうですね


この町宿での生活の中で、長崎人は初めて彼らのご馳走である
中国料理というものに お目にかかった訳で。。。
それが今日にある 【長崎卓子料理】 の始まりとなったそうですよ!!

卓子(しっぽく)料理とは 日本料理で使われている膳ではなく
テーブル(卓)に料理を乗せてそれを囲んで食べるところに特徴があって
和華蘭料理(わからん)とも評されているそうです


1570年に初めてポルトガル船が入港して以来、長い歴史の中で
外国から影響を受けて長崎風にアレンジされたレシピなのでしょうね・・・。
とにかく国際的な組み合わせになっている所がオモシロイ料理なんですよ!!
献立の中には、豚の角煮や ポルトガル伝来の冷えても美味しいという
長崎天婦羅なんかは、とにかく衣が甘くってお菓子のようでウマイッ


その他にも南蛮漬など長崎ならではの珍しい料理が登場して来ました・・・。

卓子料理の特徴として、まず最初に お鰭(おひれ)という吸物が出て来ます。
見た目や味は、お雑煮?っぽい雰囲気のメニューでしたね

これが出ると、女将さんが客人に 「おひれをどうぞ」 と挨拶をして。。。
それが済んでそこでようやく個々に宴が始まるんだそうです。
この 「おひれ」 というのは、お客様1人に魚1匹を使いました!!
という熱烈歓迎の気持ちが込められているんだとか


それだったら、おてきち流に言うと 「お頭をどうぞ!!」 ですよねぇ~



最初、卓上には1人分ずつに与えられた取り皿が2枚と箸
それとトンスイと呼ばれる陶器のサジが配られています。
その2枚の小皿で始めから終わりまで全部の料理を食べ分けるという
習わしのようですね・・・。

おてきちが何よりも1番おいしいと感じたメニューは最後に登場した
 梅椀
梅椀 と呼ばれる 御汁粉です!!
と呼ばれる 御汁粉です!!
紅白の団子と、サクラを塩漬けにした花びらが浮かせてあったのですが
もうお腹がいっぱいで何も食べられませんわ!!と思っていたのにですよ。。。
御汁粉なんて絶対に好んで食べる事のない このおてきちがですよ。。。
食べた全ての料理の中でそれも1番ウマイッ と思ったのが梅椀だったんですよ
と思ったのが梅椀だったんですよ

小豆の甘味をサラリと上品に感じさせてくれる塩サクラの存在。。。
おてきちもそんな人間になりたいです



それと、もうひとつこの富貴楼に来たかった理由に この 【諏訪祭礼図屏風】 があり
どこに飾ってあるのかと尋ねると、くんちが奉納される3日間だけ出しているそうです。
上を見上げると祭礼図屏風を額にした代替品?が飾ってあったので
とりあえず今回はコレでガマンする事に致しました



7年前に国登録有形文化財に登録された建物の中で、長崎しっぽく初デビュー!!
和華蘭料理でお腹は満たされ、歴史ある木造建築で心も満たされ
今回のゲストであった母上も、それは大いに満足であったであろうのぉ~



大海原の向こうにある異文化の国々と交流してきた長崎県の歴史は
人・食・建物など、どれをとってもそれは多彩で。。。
出合うモノ全てが鮮度が良く、またとても個性豊かなんですよねぇ



行って来ましたよん!!長崎老舗料亭 富貴楼



長崎と中国との接触は1600(慶長5)年に始まりました。
1633(寛永10)年、徳川家光は第1回の鎖国令を出し
中国の貿易船の入港許可は 長崎だけに限られたそうです


そして1689(元禄2)年に唐人屋敷が設けられ、それまで長崎市内に
散宿していた中国人は、現在の館内町の一区域に集まり住む事になりました。
中国人が長崎へ来て 唐人屋敷に移り住むまでの約80年の間
中国人が市中の町家に雑居することを、町宿(まちやど)と言ったらしく
その頃が最も市民と親密な交歓があった時代でもあるそうですね



この町宿での生活の中で、長崎人は初めて彼らのご馳走である
中国料理というものに お目にかかった訳で。。。
それが今日にある 【長崎卓子料理】 の始まりとなったそうですよ!!
卓子(しっぽく)料理とは 日本料理で使われている膳ではなく
テーブル(卓)に料理を乗せてそれを囲んで食べるところに特徴があって
和華蘭料理(わからん)とも評されているそうです



1570年に初めてポルトガル船が入港して以来、長い歴史の中で
外国から影響を受けて長崎風にアレンジされたレシピなのでしょうね・・・。
とにかく国際的な組み合わせになっている所がオモシロイ料理なんですよ!!
献立の中には、豚の角煮や ポルトガル伝来の冷えても美味しいという
長崎天婦羅なんかは、とにかく衣が甘くってお菓子のようでウマイッ



その他にも南蛮漬など長崎ならではの珍しい料理が登場して来ました・・・。
卓子料理の特徴として、まず最初に お鰭(おひれ)という吸物が出て来ます。
見た目や味は、お雑煮?っぽい雰囲気のメニューでしたね


これが出ると、女将さんが客人に 「おひれをどうぞ」 と挨拶をして。。。
それが済んでそこでようやく個々に宴が始まるんだそうです。
この 「おひれ」 というのは、お客様1人に魚1匹を使いました!!
という熱烈歓迎の気持ちが込められているんだとか



それだったら、おてきち流に言うと 「お頭をどうぞ!!」 ですよねぇ~



最初、卓上には1人分ずつに与えられた取り皿が2枚と箸
それとトンスイと呼ばれる陶器のサジが配られています。
その2枚の小皿で始めから終わりまで全部の料理を食べ分けるという
習わしのようですね・・・。
おてきちが何よりも1番おいしいと感じたメニューは最後に登場した
 梅椀
梅椀 と呼ばれる 御汁粉です!!
と呼ばれる 御汁粉です!!紅白の団子と、サクラを塩漬けにした花びらが浮かせてあったのですが
もうお腹がいっぱいで何も食べられませんわ!!と思っていたのにですよ。。。
御汁粉なんて絶対に好んで食べる事のない このおてきちがですよ。。。
食べた全ての料理の中でそれも1番ウマイッ
 と思ったのが梅椀だったんですよ
と思ったのが梅椀だったんですよ

小豆の甘味をサラリと上品に感じさせてくれる塩サクラの存在。。。
おてきちもそんな人間になりたいです



それと、もうひとつこの富貴楼に来たかった理由に この 【諏訪祭礼図屏風】 があり
どこに飾ってあるのかと尋ねると、くんちが奉納される3日間だけ出しているそうです。
上を見上げると祭礼図屏風を額にした代替品?が飾ってあったので
とりあえず今回はコレでガマンする事に致しました



7年前に国登録有形文化財に登録された建物の中で、長崎しっぽく初デビュー!!
和華蘭料理でお腹は満たされ、歴史ある木造建築で心も満たされ
今回のゲストであった母上も、それは大いに満足であったであろうのぉ~