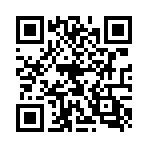島原農業高校の裏手を走って行くと、目的地である 【旧島原藩 薬園跡】 の案内板が見えて来ました。
58号線から この細い道に入る辺りには、そんなに大きな看板があったワケではなかったので
道を少々間違って、昨日の 「瓢箪畑稲荷神社」 へと突き当たったのですが。。。
でも、この辺りの地名は小山町となっているから、地名が瓢箪畑というワケではなさそうですね


しかし案内板には 「瓢箪畑風致地区」 と記されていますねぇ~・・・。
何でしょうかねぇ~、細かいことが気になります!!
とにかく・・・まずは薬草園を見学してみると致しますか



旧島原藩薬園跡は、幕末における小藩経営の薬草園ですが 当時の遺構をよくとどめた
日本三大薬園跡のひとつで、国指定の史跡だそうです

国指定の史跡となっている薬草園は、他に奈良の森野旧薬園、鹿児島の佐田旧薬園があります

森野旧薬草園には行ったことがあるけど・・・懐かしいなぁ~
しかし・・・想像していたよりも敷地が広くてビックリ!!それに手入れが行き届いてますなぁ~

長崎県文化財課の説明文によると。。。
【旧島原藩 薬園跡】
1929 (昭和4) 年 4月2日 国指定史跡となる
幕末、藩命によりシーボルトの弟子により開かれた薬園跡
現在、薬草見本園として整備されている
雲仙岳 眉山のふもとに所在する、島原藩主 松平家の御薬園跡である
下の写真に写っているのが、眉山になりますね


もちろん石垣は当時のままだそうですよ。

1842 (天保13) 年、シーボルトの門人で豊前の医師、賀来佐一郎を藩医として招き
藩士 飯島義角とともに 1846 (弘化3) 年から建設に着手し、1853 (嘉永6) 年に薬園として完成
南北約90m、東西約110mの敷地は三方を石垣で囲まれ、約1万㎡の広さがあり。。。
園内は小径によって南北に区分され、薬草畑跡は全体に東に傾き、段々畑になっているそうです


入園料は無料でしたが、入り口でパンフレットを貰ったのですが。。。
いつものように現地ではあまり目を通さずに、帰宅後に見直すということが大半なもので
よく見ると、敷地の上の方には屋敷跡&金庫跡のような場所があったみたいですね(笑)
知らなかったもので・・・写真にはありませんがアシカラズ



また2ヶ所の水溜、8基の貯蔵施設 (石積の竪穴) が残っていたりするそうで
薬草園の南手には、薬師仏をまつる2基の石厨子があるみたいですね!!
その薬師仏は、島原市宮の町の猛島神社宝物庫に納められているそうです

これまでに石垣(一部)、屋敷跡、建物跡、貯蔵穴、貯水槽などが復元され。。。
当時の面影を再現されているワケですが。。。

島原城内から移転造園された薬草園は、財政に窮乏をきたしていた時には栽培した薬草を
各藩に売って、財政を豊かにする方針もとられていたそうです


こうしてようやく完成した薬園も、廃藩と共に充分な機能を果たすことなく。。。
1869 (明治2) 年、廃止となりました。

こちらは水溜遺構のひとつで、昭和53年に修復されているみたいですね・・・。
三和土 (たたき) と記されているのは、「たたき土」 の略で、赤土・砂利などに消石灰と
にがりを混ぜて練り、塗ってたたき固めた素材3種類の材料を混ぜ合わせることから
「三和土」 と書くそうです

こういった専門的なことも色々と説明がされてありましたよ


現在は、長崎で身近に見られる薬草やハーブなど、およそ400種類が栽培されているみたいです。

「島原健康半島構想」
こういった島原藩の薬園では、薬草の栽培が行われていた歴史を背景として、薬草を地域再生の
キーワードとして、薬草を活用した新たな地域ブランドなどを考えておられるようですよ!!
薬草と聴いて思い浮かんだのは。。。伊吹もぐさかな(笑)
もぐさ餅・・・もぐら餅・・・それはないな(笑)
決して美味しくはないけれど、薬草という言葉の響きを聴くだけでも健康になった気分になる?
そんな秘めたパワーを具えているのが、薬草だと思うので。。。
色んな商品が誕生するのを、薬草ファンの1人として、おてきちも心待ちにしておりまする


58号線から この細い道に入る辺りには、そんなに大きな看板があったワケではなかったので
道を少々間違って、昨日の 「瓢箪畑稲荷神社」 へと突き当たったのですが。。。
でも、この辺りの地名は小山町となっているから、地名が瓢箪畑というワケではなさそうですね


しかし案内板には 「瓢箪畑風致地区」 と記されていますねぇ~・・・。
何でしょうかねぇ~、細かいことが気になります!!
とにかく・・・まずは薬草園を見学してみると致しますか



旧島原藩薬園跡は、幕末における小藩経営の薬草園ですが 当時の遺構をよくとどめた
日本三大薬園跡のひとつで、国指定の史跡だそうです


国指定の史跡となっている薬草園は、他に奈良の森野旧薬園、鹿児島の佐田旧薬園があります


森野旧薬草園には行ったことがあるけど・・・懐かしいなぁ~

しかし・・・想像していたよりも敷地が広くてビックリ!!それに手入れが行き届いてますなぁ~

長崎県文化財課の説明文によると。。。
【旧島原藩 薬園跡】
1929 (昭和4) 年 4月2日 国指定史跡となる
幕末、藩命によりシーボルトの弟子により開かれた薬園跡
現在、薬草見本園として整備されている
雲仙岳 眉山のふもとに所在する、島原藩主 松平家の御薬園跡である
下の写真に写っているのが、眉山になりますね



もちろん石垣は当時のままだそうですよ。
1842 (天保13) 年、シーボルトの門人で豊前の医師、賀来佐一郎を藩医として招き
藩士 飯島義角とともに 1846 (弘化3) 年から建設に着手し、1853 (嘉永6) 年に薬園として完成
南北約90m、東西約110mの敷地は三方を石垣で囲まれ、約1万㎡の広さがあり。。。
園内は小径によって南北に区分され、薬草畑跡は全体に東に傾き、段々畑になっているそうです


入園料は無料でしたが、入り口でパンフレットを貰ったのですが。。。
いつものように現地ではあまり目を通さずに、帰宅後に見直すということが大半なもので
よく見ると、敷地の上の方には屋敷跡&金庫跡のような場所があったみたいですね(笑)
知らなかったもので・・・写真にはありませんがアシカラズ



また2ヶ所の水溜、8基の貯蔵施設 (石積の竪穴) が残っていたりするそうで
薬草園の南手には、薬師仏をまつる2基の石厨子があるみたいですね!!
その薬師仏は、島原市宮の町の猛島神社宝物庫に納められているそうです


これまでに石垣(一部)、屋敷跡、建物跡、貯蔵穴、貯水槽などが復元され。。。
当時の面影を再現されているワケですが。。。
島原城内から移転造園された薬草園は、財政に窮乏をきたしていた時には栽培した薬草を
各藩に売って、財政を豊かにする方針もとられていたそうです



こうしてようやく完成した薬園も、廃藩と共に充分な機能を果たすことなく。。。
1869 (明治2) 年、廃止となりました。
こちらは水溜遺構のひとつで、昭和53年に修復されているみたいですね・・・。
三和土 (たたき) と記されているのは、「たたき土」 の略で、赤土・砂利などに消石灰と
にがりを混ぜて練り、塗ってたたき固めた素材3種類の材料を混ぜ合わせることから
「三和土」 と書くそうです


こういった専門的なことも色々と説明がされてありましたよ



現在は、長崎で身近に見られる薬草やハーブなど、およそ400種類が栽培されているみたいです。
「島原健康半島構想」
こういった島原藩の薬園では、薬草の栽培が行われていた歴史を背景として、薬草を地域再生の
キーワードとして、薬草を活用した新たな地域ブランドなどを考えておられるようですよ!!
薬草と聴いて思い浮かんだのは。。。伊吹もぐさかな(笑)
もぐさ餅・・・もぐら餅・・・それはないな(笑)
決して美味しくはないけれど、薬草という言葉の響きを聴くだけでも健康になった気分になる?
そんな秘めたパワーを具えているのが、薬草だと思うので。。。
色んな商品が誕生するのを、薬草ファンの1人として、おてきちも心待ちにしておりまする