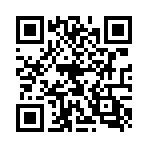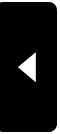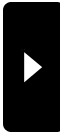2013年06月21日
「藍と白」
1970年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)において
日本民藝館(東京)が、出展したパビリオンとして設立された場所を引き継いで
民藝運動の西の拠点として、装いも新たに開館されたのが大阪日本民芸館
位置は、ちょうど太陽の塔の真後ろ辺りになりますかね

生憎の雨で、庭園などを見て回る時間がなかったのは残念でしたが。。。
目的は、特別展『BLUE & WHITE 藍と白の美―そばちょこ・藍染めを中心に』

初めて来たのですが、いきなりバランス感覚を狂わせるような三角形の敷地が出迎えてくれて
広場と呼ぶには、あまりに小さなその敷地には石が敷き詰められ、全国各地の壺・甕・鉢が
こんな感じに、ほどよく配置された簡素な野外展示場になっていましたよ。
あっ!!見っけ ここにも可愛い朝顔がこんなにもありましたよぉ~
ここにも可愛い朝顔がこんなにもありましたよぉ~



何でも、古伊万里を中心に約3000点ものそば猪口を収蔵されているそうで
それらは、大阪府藤井寺市在住の佐藤禎三氏が個人で蒐集し1979年に
寄贈されたモノだそうなんですね。今回はその中から約1000点を展示されているんですよ!!
どんな図柄のモノと出合えるのかと思うと、もう嬉しくって興奮状態が止まりません


どうして、白地に呉須(藍色の顔料)で模様を描いた染付の磁器に惹かれるのか
いくら考えても答えは見つかりません・・・。
だけど見ているだけで、恋しくて、ドキドキして、楽しい気持ちで全身が満たされるんですよ

図柄としては、植物、動物、家紋、風景、唐草、唐子など。。。
中には図柄が、ぼやっとした仕上がり感が癒し系の(コンニャク印判)そば猪口があって
なかなかお目に掛かれないだけあって、そのモノの時代の趣を感じましたねぇ~・・・。
着慣れた普段着に包まれるような素朴な温もりの中、それでいてモダンな雰囲気もあって
日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品。。。
まさに『用の美』が肩を並べて、個性ある表情で束の間の幸福感を愉しませて頂きました


日本民藝館(東京)が、出展したパビリオンとして設立された場所を引き継いで
民藝運動の西の拠点として、装いも新たに開館されたのが大阪日本民芸館

位置は、ちょうど太陽の塔の真後ろ辺りになりますかね


生憎の雨で、庭園などを見て回る時間がなかったのは残念でしたが。。。
目的は、特別展『BLUE & WHITE 藍と白の美―そばちょこ・藍染めを中心に』
初めて来たのですが、いきなりバランス感覚を狂わせるような三角形の敷地が出迎えてくれて
広場と呼ぶには、あまりに小さなその敷地には石が敷き詰められ、全国各地の壺・甕・鉢が
こんな感じに、ほどよく配置された簡素な野外展示場になっていましたよ。
あっ!!見っけ
 ここにも可愛い朝顔がこんなにもありましたよぉ~
ここにも可愛い朝顔がこんなにもありましたよぉ~


何でも、古伊万里を中心に約3000点ものそば猪口を収蔵されているそうで
それらは、大阪府藤井寺市在住の佐藤禎三氏が個人で蒐集し1979年に
寄贈されたモノだそうなんですね。今回はその中から約1000点を展示されているんですよ!!
どんな図柄のモノと出合えるのかと思うと、もう嬉しくって興奮状態が止まりません



どうして、白地に呉須(藍色の顔料)で模様を描いた染付の磁器に惹かれるのか
いくら考えても答えは見つかりません・・・。
だけど見ているだけで、恋しくて、ドキドキして、楽しい気持ちで全身が満たされるんですよ


図柄としては、植物、動物、家紋、風景、唐草、唐子など。。。
中には図柄が、ぼやっとした仕上がり感が癒し系の(コンニャク印判)そば猪口があって
なかなかお目に掛かれないだけあって、そのモノの時代の趣を感じましたねぇ~・・・。
着慣れた普段着に包まれるような素朴な温もりの中、それでいてモダンな雰囲気もあって
日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品。。。
まさに『用の美』が肩を並べて、個性ある表情で束の間の幸福感を愉しませて頂きました



Posted by
おてきち
at
09:24
│
Comments(
4
)
│
陶芸・焼物
この記事へのコメント
雨ですね。台風と出発して、新しい台風を持って帰ってきた。京都行きをあきらめています。
軽トラで行き、乗せていた自転車で回るのが美術館の足ですが、雨はだめ。
‘70年の万博で、日本庭園の日本建築に、花生けの仕事に行きました。もちろん、手伝い。日本館のほかに、民芸館ってありましたかね・・・今はどこかな。今も公園内にあるのですか。
軽トラで行き、乗せていた自転車で回るのが美術館の足ですが、雨はだめ。
‘70年の万博で、日本庭園の日本建築に、花生けの仕事に行きました。もちろん、手伝い。日本館のほかに、民芸館ってありましたかね・・・今はどこかな。今も公園内にあるのですか。
Posted by
た
at
2013年06月21日 13:46
万博が開催されていた頃は、まだおてきちの存在は無かったですね(-_-+)
その頃、た様は花生けの作法?に全力投球中だったなんて、手伝いとは言ってもカッコいいですよ!!
オモロ流と呼ばれる、おてきちの我流には負けると思いますけど♪ なぁ~んてね(^-^)
確か、あの広過ぎる公園内に日本民芸館はありましたよ。
他を見て回る事もなく、高い駐車料金を払って?目的のみを済ませて退散しましたもので。。。
また機会を見付けて、一度、日本庭園を見学したいものですね。
その頃、た様は花生けの作法?に全力投球中だったなんて、手伝いとは言ってもカッコいいですよ!!
オモロ流と呼ばれる、おてきちの我流には負けると思いますけど♪ なぁ~んてね(^-^)
確か、あの広過ぎる公園内に日本民芸館はありましたよ。
他を見て回る事もなく、高い駐車料金を払って?目的のみを済ませて退散しましたもので。。。
また機会を見付けて、一度、日本庭園を見学したいものですね。
Posted by
おてきち at
2013年06月21日 23:41
at
2013年06月21日 23:41
 at
2013年06月21日 23:41
at
2013年06月21日 23:41
「猪口」は、逆台形の形が、猪の口に似ているため、当初は「猪口(ちょく)」と呼ばれていた。17世紀前期頃は、用途は向こう付け。おかずを入れる容器として使用された。おかず入れなので、口径も7㎝より大きめ。現存する最古の猪口の一つは、1655~1670年ごろのもので、東大埋蔵文化財調査室に所蔵されている染付松文の猪口。18世紀になると、次第に雑器として庶民にも使用されるようになる。口径は7㎝くらいになる。江戸後期には、蕎麦屋が大流行し、江戸だけで4千軒近くの蕎麦屋があったいう。そこでは、付け汁を入れる器として、また、酒を飲む器として使用された。柳宗悦は、「一番驚くのは文様の変化である。この蕎麦猪口くらい衣装持ちは無いと言える。いかに日本人が自然を友にしたかが分かる。」と「藍絵の猪口」の中で語っている。
Posted by
ハチ
at
2013年06月22日 09:06
いいですねぇ~!!いい!!最高です(^-^)
18世紀以降は、日本の外食産業が盛んになって加速的にそば猪口の生産・流通が
活発となり、そば食も増えて行ったそうですね。
地域差はあるそうですが、うどん中心でそば食が盛んでなかった地域では
そば猪口の出土量も少なかったそうです。
そう考えると、食文化との兼ね合いも大切なんですよね(^-^)
大好きな蕎麦と蕎麦猪口。。。命の次に大切な世界ですよね!!
18世紀以降は、日本の外食産業が盛んになって加速的にそば猪口の生産・流通が
活発となり、そば食も増えて行ったそうですね。
地域差はあるそうですが、うどん中心でそば食が盛んでなかった地域では
そば猪口の出土量も少なかったそうです。
そう考えると、食文化との兼ね合いも大切なんですよね(^-^)
大好きな蕎麦と蕎麦猪口。。。命の次に大切な世界ですよね!!
Posted by
おてきち at
2013年06月23日 11:03
at
2013年06月23日 11:03
 at
2013年06月23日 11:03
at
2013年06月23日 11:03