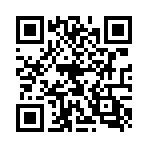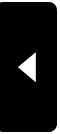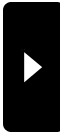2013年06月20日
煮売茶船
旅人の1番の楽しみと言えば、もちろん食事でしょ!!
江戸時代を通して、大坂・京都間のほぼ半ばにある枚方宿では当時
休憩や食事をとる場所として、賑わっていたそうですね

オランダ東インド会社の商館長の江戸参府に、医師として随行したシーボルトの記録によれば
「枚方の環境は非常に美しく、淀川の地域は私に祖国のマインの谷を思い出させる所が多い」
そのような事が案内板には書かれていました。

ここから少し歩いて行くと、市立枚方宿鍵屋資料館があります。
この鍵屋は、伏見と大坂を結ぶ三十石船の船宿として江戸時代は賑い
近年まで料亭をされていたそうなんですね

この主屋を解体修理し、江戸時代の姿に復元する際に発掘された出土品の数々が
資料館には展示されていて、淀川水運で活躍をした【くらわんか舟】の模型もありました。

【淀川三十石船唄】には「鍵屋浦には碇(いかり)は要らぬ 三味や太鼓で船止める」
なぁ~んて粋な具合に謡われていたようですね



出土品の中に【くらわんか茶碗】というのが いくつもあって。。。
これは、長崎県波佐見市で作られたものも数多く含まれているんですよね・・・。
もしかして、シーボルト先生がお土産にでもと置いて行ったのでしょうかね



淀川を上下する客船三十石船と、その船客相手に乱暴な言葉使いで飲食物を商いする
くらわんか舟の売り手と、買い手とのやり取りが長旅をする者の楽しみでもあったそうです
唯一、許された淀川上での乱暴な言葉使いの商いは、御法度どころか。。。
淀川名物として、

 OKだったみたいですネ
OKだったみたいですネ



歌川広重が画いた【三十石船とくらわんか舟】
手前の小舟で、ゴボウ汁や餅などを温めながら。。。
「食うたらんかいっ!!」、「買うたらんかいっ!!」
などと強気の商いが、実に面白い


しかし、そんなふうに言われて買う客人の気持ちが、「サッパリ分からない・・・」
とにかく、現地で発掘されたリアルな出土品の魅力に触れる事が出来て最高でした

江戸時代を通して、大坂・京都間のほぼ半ばにある枚方宿では当時
休憩や食事をとる場所として、賑わっていたそうですね


オランダ東インド会社の商館長の江戸参府に、医師として随行したシーボルトの記録によれば
「枚方の環境は非常に美しく、淀川の地域は私に祖国のマインの谷を思い出させる所が多い」
そのような事が案内板には書かれていました。
ここから少し歩いて行くと、市立枚方宿鍵屋資料館があります。
この鍵屋は、伏見と大坂を結ぶ三十石船の船宿として江戸時代は賑い
近年まで料亭をされていたそうなんですね


この主屋を解体修理し、江戸時代の姿に復元する際に発掘された出土品の数々が
資料館には展示されていて、淀川水運で活躍をした【くらわんか舟】の模型もありました。
【淀川三十石船唄】には「鍵屋浦には碇(いかり)は要らぬ 三味や太鼓で船止める」
なぁ~んて粋な具合に謡われていたようですね



出土品の中に【くらわんか茶碗】というのが いくつもあって。。。
これは、長崎県波佐見市で作られたものも数多く含まれているんですよね・・・。
もしかして、シーボルト先生がお土産にでもと置いて行ったのでしょうかね



淀川を上下する客船三十石船と、その船客相手に乱暴な言葉使いで飲食物を商いする
くらわんか舟の売り手と、買い手とのやり取りが長旅をする者の楽しみでもあったそうです

唯一、許された淀川上での乱暴な言葉使いの商いは、御法度どころか。。。
淀川名物として、


 OKだったみたいですネ
OKだったみたいですネ


歌川広重が画いた【三十石船とくらわんか舟】
手前の小舟で、ゴボウ汁や餅などを温めながら。。。
「食うたらんかいっ!!」、「買うたらんかいっ!!」
などと強気の商いが、実に面白い



しかし、そんなふうに言われて買う客人の気持ちが、「サッパリ分からない・・・」
とにかく、現地で発掘されたリアルな出土品の魅力に触れる事が出来て最高でした


Posted by
おてきち
at
08:34
│
Comments(
4
)
│
建造物
この記事へのコメント
落語の一節で聞いたような‥‥
で、その「椀」ってのは、陶器ですか。木椀で、割れない奴だった‥‥てなことは無く、プラスチックでもない。
結構、割れたり落としたりして‥‥お金も落としたりしたんじゃないですかね。
で、その「椀」ってのは、陶器ですか。木椀で、割れない奴だった‥‥てなことは無く、プラスチックでもない。
結構、割れたり落としたりして‥‥お金も落としたりしたんじゃないですかね。
Posted by
た
at
2013年06月20日 18:14
「椀」ではなく「ワン♪」でもなく、「碗」の方ですね(^-^)
大半が陶磁器ですが、ほぼ雑器に近い器なんでしょうかね。
「峠の釜飯」みたいな雰囲気で使われていたと思うと分かりやすいカモ知れませんが。。。
比較的、分厚い目の深さ3センチくらいのものから、お茶碗ふうのものまで様々でしたね。
割れた器の継ぎ目跡に、違和感どころか愛着を感じるようなドッシリ系の器が目立ったかな。
大半が陶磁器ですが、ほぼ雑器に近い器なんでしょうかね。
「峠の釜飯」みたいな雰囲気で使われていたと思うと分かりやすいカモ知れませんが。。。
比較的、分厚い目の深さ3センチくらいのものから、お茶碗ふうのものまで様々でしたね。
割れた器の継ぎ目跡に、違和感どころか愛着を感じるようなドッシリ系の器が目立ったかな。
Posted by
おてきち at
2013年06月21日 09:43
at
2013年06月21日 09:43
 at
2013年06月21日 09:43
at
2013年06月21日 09:43
宝塚の花組で、「くらわんか」という公演があり、古典落語を基にしている。この枚方の船宿が舞台だから、おそらく「鍵屋」ではないだろうか・・・・幽霊の小糸さんまでもが登場する荒唐無稽の話だ。「飯食らわんか・・・・酒食らわんか・・・・」。聞こえてきそうな建物だな。「淀の上手の千両松は 売らず買わずで 見て千両(ヤレサ ヨイヨイヨーイ)・・・・・・・」
Posted by
ハチ
at
2013年06月22日 09:36
それにしても幅が広い話ですねぇ~(^-^)
そういえば、この枚方宿の周辺に「くらわんか整骨院」というのがありましたよ!!
ビックリです・・・。
この名前を前後逆にした場合、「整骨院くらわんか」になりますが。。。
それって、整えた骨を食う??? おてきち、ちょっと くらわんかバカになってしまっているようですね・・・。
頭を冷やして、出直して参りましょうかね(笑) ふふふっ♪
そういえば、この枚方宿の周辺に「くらわんか整骨院」というのがありましたよ!!
ビックリです・・・。
この名前を前後逆にした場合、「整骨院くらわんか」になりますが。。。
それって、整えた骨を食う??? おてきち、ちょっと くらわんかバカになってしまっているようですね・・・。
頭を冷やして、出直して参りましょうかね(笑) ふふふっ♪
Posted by
おてきち at
2013年06月23日 11:12
at
2013年06月23日 11:12
 at
2013年06月23日 11:12
at
2013年06月23日 11:12