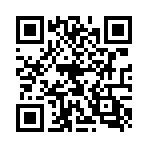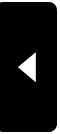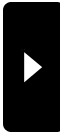2021年05月04日
竹皮べっ甲
この時期になるとお隣さんから頂くのが、鹿児島県の郷土料理【あくまき】
材料は、もち米、灰汁(アク汁)、竹の皮
そういえば長崎のJAにも、竹の皮が売られていましたよ



「あくまき」とは、主に端午の節句で食べられる所謂「ちまき」のことですが
長崎にも「唐あくちまき」というのが売ってあって、それはこの形状にほぼ近いですね。
でも和菓子屋さんで売られている「長崎ちまき」は、竹の皮ではなくサラシに包まれて
炊き上げられた状態のまま、売られているのもありますね



そしてこの鹿児島で作られている餅菓子「あくまき」の歴史は、関ヶ原の戦いの際
薩摩藩主である島津義弘公が、日持ちのする食糧として持参したのが始まりなんだとか

また西郷どんも、西南戦争で食べていたそうですから。。。
そういった背景から、男子が強くたくましく育つようにという願いを込めて
端午の節句に食べられるようになったそうですよ



竹の皮を開いてみると、これが結構ベタベタ&ネットリとしていて扱いが大変です(笑)
主人が帰宅してから切って貰ったのですが。。。
包丁で切るのではなく、タコ糸で切っていましたからね・・・さすがジゲモンです


竹の皮もネトネトしていたけど、太陽の光を通してカメラを構えたら。。。
まるでべっ甲のようでしょ




作り方としては、もち米を木や竹を燃やして出た灰からとった灰汁(アク)に浸したあと
もち米を孟宗竹の皮で包んで、灰汁水で数時間煮込むそうです

灰汁に含まれるアルカリ性物質が、もち米の繊維をやわらかくするそうですね・・・。
米粒が、このようなべっ甲色に変化しているのって、灰汁による化学変化なんでしょうかね?
伝統食や郷土料理を知れば知るほどに、今のネット時代に頼り切っている人間からすれば
昔の人の知恵には、ホント感心させられますよね



食べ方としては、白砂糖やきな粉をまぶして食べたり、黒蜜をかけて食べたりするそうです。
おてきちは、ちょっと癖のあるアクのニオイ?というか・・・
薬品のようなニオイが鼻について苦手なんです(アクまで個人的な味覚による感想ですが
 )
)
そういえば、砂糖醤油をつけて食べるところもあるそうなので。。。
それなら馴染みのある食べ方だし、ニオイも気にならないカモ!!

材料は、もち米、灰汁(アク汁)、竹の皮
そういえば長崎のJAにも、竹の皮が売られていましたよ



「あくまき」とは、主に端午の節句で食べられる所謂「ちまき」のことですが
長崎にも「唐あくちまき」というのが売ってあって、それはこの形状にほぼ近いですね。
でも和菓子屋さんで売られている「長崎ちまき」は、竹の皮ではなくサラシに包まれて
炊き上げられた状態のまま、売られているのもありますね



そしてこの鹿児島で作られている餅菓子「あくまき」の歴史は、関ヶ原の戦いの際
薩摩藩主である島津義弘公が、日持ちのする食糧として持参したのが始まりなんだとか


また西郷どんも、西南戦争で食べていたそうですから。。。
そういった背景から、男子が強くたくましく育つようにという願いを込めて
端午の節句に食べられるようになったそうですよ



竹の皮を開いてみると、これが結構ベタベタ&ネットリとしていて扱いが大変です(笑)
主人が帰宅してから切って貰ったのですが。。。
包丁で切るのではなく、タコ糸で切っていましたからね・・・さすがジゲモンです



竹の皮もネトネトしていたけど、太陽の光を通してカメラを構えたら。。。
まるでべっ甲のようでしょ




作り方としては、もち米を木や竹を燃やして出た灰からとった灰汁(アク)に浸したあと
もち米を孟宗竹の皮で包んで、灰汁水で数時間煮込むそうです


灰汁に含まれるアルカリ性物質が、もち米の繊維をやわらかくするそうですね・・・。
米粒が、このようなべっ甲色に変化しているのって、灰汁による化学変化なんでしょうかね?
伝統食や郷土料理を知れば知るほどに、今のネット時代に頼り切っている人間からすれば
昔の人の知恵には、ホント感心させられますよね



食べ方としては、白砂糖やきな粉をまぶして食べたり、黒蜜をかけて食べたりするそうです。
おてきちは、ちょっと癖のあるアクのニオイ?というか・・・
薬品のようなニオイが鼻について苦手なんです(アクまで個人的な味覚による感想ですが

 )
)そういえば、砂糖醤油をつけて食べるところもあるそうなので。。。
それなら馴染みのある食べ方だし、ニオイも気にならないカモ!!
Posted by
おてきち
at
15:46
│
Comments(
2
)
│
和菓子
この記事へのコメント
竹の皮はホントに無くなった。でも、竹藪に入って自分で集めたことは無い。煮詰めて乾燥・・・皮に適度な湿度を残すのが難しいらしい。
ことしも今週末、ビニールで代用し、漬ける事を決めました。腰に不安はありますが、注意に注意を払ってです・・・年末に期待してください。
ことしも今週末、ビニールで代用し、漬ける事を決めました。腰に不安はありますが、注意に注意を払ってです・・・年末に期待してください。
Posted by
た
at
2021年05月05日 07:40
た様
竹皮って煮詰めて乾燥させるんですか・・・知らなかった。
で、今年も頑張るのですか!?大丈夫ですか(-_-+)
ホント、それで腰を痛めては大変ですからね。。。
助手として参加できない(お役に立てない)のが申し訳ない。
もちろん厚かましくも期待しておりますが♬
何なら母を派遣致しましょうか(笑)た様が腰を痛めた時のためにね(^-^)
でも、くれぐれも慎重に漬けて下さいよ!!
竹皮って煮詰めて乾燥させるんですか・・・知らなかった。
で、今年も頑張るのですか!?大丈夫ですか(-_-+)
ホント、それで腰を痛めては大変ですからね。。。
助手として参加できない(お役に立てない)のが申し訳ない。
もちろん厚かましくも期待しておりますが♬
何なら母を派遣致しましょうか(笑)た様が腰を痛めた時のためにね(^-^)
でも、くれぐれも慎重に漬けて下さいよ!!
Posted by
おてきち at
2021年05月05日 14:58
at
2021年05月05日 14:58
 at
2021年05月05日 14:58
at
2021年05月05日 14:58