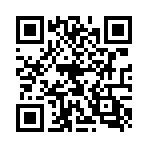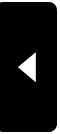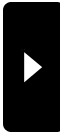長崎出身の日本画家 【松尾敏男】 (1926~2016) の没後初の回顧展が開催されていたので
久しぶりに美術鑑賞がてら、ロクと離れ離れの時間を過ごして参りました(笑)
恥ずかしながら、おてきちは松尾氏について無知でして。。。
パンフレットで見た牡丹の絵と、「長崎旅情」 という稲佐山から見た長崎の街の夜景が
大きな屏風に描かれた作品を見たかっただけなのですが。。。経歴を見てビックリです


日本画界の重鎮で文化勲章受章!!
一度も途切れることなく 院展に作品を発表し続けた!!
日本美術院を主な舞台として活動し、平山郁夫氏が亡き後、理事長職を引き継いで
日本画壇を牽引する存在として活躍された人物が、長崎出身だったとは。。。
そして師事されていたのは、あの 【堅山南風】 なんだそうですよ


展示作品の中には花鳥画以外にも、インド、中国、ヨーロッパといった海外で取材された動物画や
南風先生の肖像画だったりと、松尾氏本人が リストアップされていた作品を中心に構成されている
展示内容だけあって、迫力のある作品から空気感が感じられる柔らかな作品まで、とにかく幅広い
画業の集大成が観られて大満足でしたね・・・。
その中でも印象に残ったのは・・・やっぱり初めて見た 院展最後の出品作となった 「玄皎想」
水墨の濃淡で ボカシふうに描かれた牡丹の葉っぱが、背景の余白によって浮かび上がるように見えて
その葉っぱに包み込まれるように描かれた、牡丹の花たちが眩しすぎて。。。胡粉でしょうね?
牡丹なのに、なぜか闇夜に浮かぶ月下美人を観たような・・・
絵画なのに近寄りがたい気品というか、これが目指されていた牡丹の品格なのでしょうね



松尾は晩年、水墨画を志向していた。
題名の 「玄皎 (げんこう)」 とは黒と白を意味する。
昭和30年代に当時の日本美術院同人らによって、水墨の世界を重んじようという研究会 「玄皎会」
が催され、横山大観や堅山南風も参加した。
つまり本作は、水墨への想いとともに 古の院展作家たちへ想いを馳せている。
体調の悪化から、筆の進まない日が幾日も続いた。
渾身の力を振り絞って描かれた本作は、水墨、そして余白の美を追求したまさに日本画の王道と
呼ぶべきものとなった。
~中略~
終生こだわり続けた牡丹の絵を最後に、70年に及ぶ画業は静かに 幕を閉 じた。
牡丹の下で安らかに眠る猫が、松尾自身と重なってみえるのは私だけではないだろう。
参考資料 (長崎県美術館 学芸員・森園敦) より抜粋

久しぶりに美術鑑賞がてら、ロクと離れ離れの時間を過ごして参りました(笑)
恥ずかしながら、おてきちは松尾氏について無知でして。。。
パンフレットで見た牡丹の絵と、「長崎旅情」 という稲佐山から見た長崎の街の夜景が
大きな屏風に描かれた作品を見たかっただけなのですが。。。経歴を見てビックリです



日本画界の重鎮で文化勲章受章!!
一度も途切れることなく 院展に作品を発表し続けた!!
日本美術院を主な舞台として活動し、平山郁夫氏が亡き後、理事長職を引き継いで
日本画壇を牽引する存在として活躍された人物が、長崎出身だったとは。。。
そして師事されていたのは、あの 【堅山南風】 なんだそうですよ


展示作品の中には花鳥画以外にも、インド、中国、ヨーロッパといった海外で取材された動物画や
南風先生の肖像画だったりと、松尾氏本人が リストアップされていた作品を中心に構成されている
展示内容だけあって、迫力のある作品から空気感が感じられる柔らかな作品まで、とにかく幅広い
画業の集大成が観られて大満足でしたね・・・。
その中でも印象に残ったのは・・・やっぱり初めて見た 院展最後の出品作となった 「玄皎想」
水墨の濃淡で ボカシふうに描かれた牡丹の葉っぱが、背景の余白によって浮かび上がるように見えて
その葉っぱに包み込まれるように描かれた、牡丹の花たちが眩しすぎて。。。胡粉でしょうね?
牡丹なのに、なぜか闇夜に浮かぶ月下美人を観たような・・・
絵画なのに近寄りがたい気品というか、これが目指されていた牡丹の品格なのでしょうね



松尾は晩年、水墨画を志向していた。
題名の 「玄皎 (げんこう)」 とは黒と白を意味する。
昭和30年代に当時の日本美術院同人らによって、水墨の世界を重んじようという研究会 「玄皎会」
が催され、横山大観や堅山南風も参加した。
つまり本作は、水墨への想いとともに 古の院展作家たちへ想いを馳せている。
体調の悪化から、筆の進まない日が幾日も続いた。
渾身の力を振り絞って描かれた本作は、水墨、そして余白の美を追求したまさに日本画の王道と
呼ぶべきものとなった。
~中略~
終生こだわり続けた牡丹の絵を最後に、70年に及ぶ画業は静かに 幕を閉 じた。
牡丹の下で安らかに眠る猫が、松尾自身と重なってみえるのは私だけではないだろう。
参考資料 (長崎県美術館 学芸員・森園敦) より抜粋
ステンドグラスといえば・・・やっぱり思い浮かぶのは教会の窓に嵌め込まれた
キリストの誕生や洗礼から生涯までといった、聖書の風景が描かれたものが
印象的ではありますね


その他にも、美しいステンドグラスのランプもありますよね


ランプの図柄は、バラや花のモチーフといった華やかなものが目立ちますが。。。

ランプといえば、色と光りを制することがステンドグラスを単なるガラスの工業製品から
鑑賞できる工芸品へと高めた 【ティファニー】 や 【リチャード・リー】 の作品が有名ですが
あのようにコッテリ・とんこつ系も、それはそれで良いと思うのですが。。。
おてきちは、サッパリ・塩系もしくはあごだしベースの方が毎日食べても飽きないというか
えっ?何の話ですか?って(笑) ラーメンの話ではなかったですね



実は、こんな雰囲気のシンプルで無骨?なランプを探していたんですよねぇ~!!
先日、大浦天主堂方面に出掛けたのですが、そっち方面に行った時には必ず立ち寄る
ガラスショップがあって、そこで見つけたのが今日の写真のステンドグラスランプなんです
どこにでもありそうなんですけど・・・意外と無いタイプだと おてきちは思ってるんですけどね(笑)
何分、何十分でも この柔らかな光だったら眺めていられそう・・・かな



キリストの誕生や洗礼から生涯までといった、聖書の風景が描かれたものが
印象的ではありますね



その他にも、美しいステンドグラスのランプもありますよね



ランプの図柄は、バラや花のモチーフといった華やかなものが目立ちますが。。。
ランプといえば、色と光りを制することがステンドグラスを単なるガラスの工業製品から
鑑賞できる工芸品へと高めた 【ティファニー】 や 【リチャード・リー】 の作品が有名ですが
あのようにコッテリ・とんこつ系も、それはそれで良いと思うのですが。。。
おてきちは、サッパリ・塩系もしくはあごだしベースの方が毎日食べても飽きないというか
えっ?何の話ですか?って(笑) ラーメンの話ではなかったですね



実は、こんな雰囲気のシンプルで無骨?なランプを探していたんですよねぇ~!!
先日、大浦天主堂方面に出掛けたのですが、そっち方面に行った時には必ず立ち寄る
ガラスショップがあって、そこで見つけたのが今日の写真のステンドグラスランプなんです

どこにでもありそうなんですけど・・・意外と無いタイプだと おてきちは思ってるんですけどね(笑)
何分、何十分でも この柔らかな光だったら眺めていられそう・・・かな



今朝も起きたら雪が庭や階段に・・・薄っすらと積もってましたよ


昨日も、薄っすらと雪化粧に染まった長崎の街でしたが。。。
それにしても、こんなに連日、雪が降るなんてねぇ~、嬉しいやら、寒いやら



庭の 「きんかん」 や 「南天の実」 を狙って、色んな小鳥が裏山から飛んで来ています。
音を立てると、すぐに逃げて行ってしまうので・・・静かにガラス戸越しに撮った写真です

寒いので、羽の間に空気をいっぱい取り込んで体を膨らませていましたよ(笑)

ふくら雀みたいにコロンと太った可愛い小鳥ですが。。。名前を調べてみたところ
恐らく 【ジョウビタキ】 だと思いますが、オスの胸や腹は橙色で メスは黄褐色のようなので。。。
この小鳥はオスってことでしょうかね



今日も寒かったですが、明日からは日中最高気温が15度もあるみたいなので花粉情報が
気になる季節となって来ましたよ・・・。
そうだった!!その前に早く フキノトウを探しに行かなくっちゃ





昨日も、薄っすらと雪化粧に染まった長崎の街でしたが。。。
それにしても、こんなに連日、雪が降るなんてねぇ~、嬉しいやら、寒いやら



庭の 「きんかん」 や 「南天の実」 を狙って、色んな小鳥が裏山から飛んで来ています。
音を立てると、すぐに逃げて行ってしまうので・・・静かにガラス戸越しに撮った写真です


寒いので、羽の間に空気をいっぱい取り込んで体を膨らませていましたよ(笑)
ふくら雀みたいにコロンと太った可愛い小鳥ですが。。。名前を調べてみたところ

恐らく 【ジョウビタキ】 だと思いますが、オスの胸や腹は橙色で メスは黄褐色のようなので。。。
この小鳥はオスってことでしょうかね



今日も寒かったですが、明日からは日中最高気温が15度もあるみたいなので花粉情報が
気になる季節となって来ましたよ・・・。
そうだった!!その前に早く フキノトウを探しに行かなくっちゃ



神社のハシゴは続いております(笑)
中島川に架かる伊勢宮神社前の 「高麗橋」 よりもひとつ上流の橋である 「阿弥陀橋」 を渡って
細い路地道のような通りを歩いて行くと、以前にもブログにアップしたことがありますが
おてきちの大好きな陶製鳥居のある 【宮地嶽八幡神社】 があります


まさか、ここへロクと一緒に来ることが出来るとは・・・思いもしませんでしたが。。。
とにかく嬉しい限りなので、記念に1枚


八幡(やはた)町にある 宮地嶽八幡神社は、今回の九社スタンプラリーの中には
入っていないのですが、御朱印を貰っておこうと思い立ち寄ったところ。。。
こちらもお留守・・・のようでしたので、また後日改めて来ることに致しました


こんなに大きな手水にまで、氷がビッシリとはってましたよ・・・。

それで、マイ御朱印帖がコレなのですが。。。
1番最初に書いて貰った日付を見直すと、「平成17年 9月 6日」 でした・・・。
ということは、約13年前ということになりますかねぇ~。
お寺の御朱印は、神社よりも前から始めていたから、もう何年前になるのかなぁ~。
しかもこの御朱印帖を買ったのは、京都の清明神社でしたからね(笑)
相変わらずマニアックな趣味ですわ



そして今回、長崎の神社巡りの中で衝撃的な御朱印と出合ったもので。。。
ちょっとご紹介させて頂きたく候!!
それがこちらの 【中川八幡神社】 さんの御朱印になります


右下の方にドラエモンのイラストが描いてあるでしょ!?
おてきちが無理を言って、ドラエモンをオーダーした訳じゃないんですよ(笑)

先方さんがイラストが得意なので、おひとついかがでしょうか?という話だったので。。。
最初は、何を描いて欲しいのかをこちらが伝えるのかな?と思っていたら違っていて
ドラエモンは夢を叶えてくれるアイテム?のようなものだから、縁起が良いといった
感じで話は進んでいたように思いますが


御朱印を描いて頂いた人物は、そういえば左利きでしたね、そして色つきのドラエモンですし(笑)
斬新というのか、前衛?というべきか・・・長崎らしい文化に触れた今回の神社巡りでしたね!!
中島川に架かる伊勢宮神社前の 「高麗橋」 よりもひとつ上流の橋である 「阿弥陀橋」 を渡って
細い路地道のような通りを歩いて行くと、以前にもブログにアップしたことがありますが
おてきちの大好きな陶製鳥居のある 【宮地嶽八幡神社】 があります



まさか、ここへロクと一緒に来ることが出来るとは・・・思いもしませんでしたが。。。
とにかく嬉しい限りなので、記念に1枚


八幡(やはた)町にある 宮地嶽八幡神社は、今回の九社スタンプラリーの中には
入っていないのですが、御朱印を貰っておこうと思い立ち寄ったところ。。。
こちらもお留守・・・のようでしたので、また後日改めて来ることに致しました



こんなに大きな手水にまで、氷がビッシリとはってましたよ・・・。
それで、マイ御朱印帖がコレなのですが。。。
1番最初に書いて貰った日付を見直すと、「平成17年 9月 6日」 でした・・・。
ということは、約13年前ということになりますかねぇ~。
お寺の御朱印は、神社よりも前から始めていたから、もう何年前になるのかなぁ~。
しかもこの御朱印帖を買ったのは、京都の清明神社でしたからね(笑)
相変わらずマニアックな趣味ですわ



そして今回、長崎の神社巡りの中で衝撃的な御朱印と出合ったもので。。。
ちょっとご紹介させて頂きたく候!!
それがこちらの 【中川八幡神社】 さんの御朱印になります



右下の方にドラエモンのイラストが描いてあるでしょ!?
おてきちが無理を言って、ドラエモンをオーダーした訳じゃないんですよ(笑)
先方さんがイラストが得意なので、おひとついかがでしょうか?という話だったので。。。
最初は、何を描いて欲しいのかをこちらが伝えるのかな?と思っていたら違っていて
ドラエモンは夢を叶えてくれるアイテム?のようなものだから、縁起が良いといった
感じで話は進んでいたように思いますが



御朱印を描いて頂いた人物は、そういえば左利きでしたね、そして色つきのドラエモンですし(笑)
斬新というのか、前衛?というべきか・・・長崎らしい文化に触れた今回の神社巡りでしたね!!
若宮稲荷さんから下って歩いて、お次に目指した先は 【伊勢宮】 です。
伊勢宮は、諏訪神社、松森神社とともに長崎三社のひとつ言われるお宮さんで
1629 (寛永6) 年に、伊勢の内宮の神 「天照皇大神」 の御分霊を
1639 (寛永16) 年に、外宮の神 「豊受大師」 の御分霊を勧請して
祀ったことに始まる、とスタンプラリーの台紙に説明がありました


また、お宮さんのあちらこちらで見かける 「大一」 という文字ですが。。。
それは伊勢神宮の古い神紋で、長崎の伊勢宮でも古くより神紋として使用されてきたそうです。
写真では分かり辛いのですが。。。掛燈籠にも 「大一」 という文字が中央に
刻まれていて、その底には寄贈主 「丸山町 花月」 の名前がありましたよ!!

その他にも拝殿の両側の頭上には、36枚の少々色褪せた額絵が掛けられていましたが
説明によると、江戸時代末期の1696 (元禄9) 年 に、長崎貿易で莫大な富を得た京都の商人
伏見屋四郎兵衛から奉納されたモノだそうです

紀貫之、小野小町、平清盛などが詠んだ 36首の歌と肖像画が描かれている雅な額絵でしたよ



境内から右の奥へ進むと、ひときわ存在感を放つ御神木、クスノキでしょうかね?
幹部分には洞窟のような穴が空いていましたけど・・・どうもそれは江戸時代頃の火災で
焼けたらしいと言われていますが。。。
このクスノキには、御神木と呼ばれるに相応しい逸話が残されているそうですよ



その昔、子どもを産んで お乳がでない母親が、洞穴のように穴が空いているクスノキの幹に
お米のとぎ汁を一升かけ、お祈りをすると お乳が出るようになったということから
その後、お乳がでない母親たちが多く参拝に訪れるようになったと言われています。
それが、安産祈願で訪れる参拝者が多い由縁カモ!?ということでした


長崎の神社には、必ず1本はこのような逸話を持った 巨大なクスノキが立っていますね・・・。
伊勢宮は、諏訪神社、松森神社とともに長崎三社のひとつ言われるお宮さんで
1629 (寛永6) 年に、伊勢の内宮の神 「天照皇大神」 の御分霊を
1639 (寛永16) 年に、外宮の神 「豊受大師」 の御分霊を勧請して
祀ったことに始まる、とスタンプラリーの台紙に説明がありました


また、お宮さんのあちらこちらで見かける 「大一」 という文字ですが。。。
それは伊勢神宮の古い神紋で、長崎の伊勢宮でも古くより神紋として使用されてきたそうです。
写真では分かり辛いのですが。。。掛燈籠にも 「大一」 という文字が中央に
刻まれていて、その底には寄贈主 「丸山町 花月」 の名前がありましたよ!!
その他にも拝殿の両側の頭上には、36枚の少々色褪せた額絵が掛けられていましたが
説明によると、江戸時代末期の1696 (元禄9) 年 に、長崎貿易で莫大な富を得た京都の商人
伏見屋四郎兵衛から奉納されたモノだそうです


紀貫之、小野小町、平清盛などが詠んだ 36首の歌と肖像画が描かれている雅な額絵でしたよ



境内から右の奥へ進むと、ひときわ存在感を放つ御神木、クスノキでしょうかね?
幹部分には洞窟のような穴が空いていましたけど・・・どうもそれは江戸時代頃の火災で
焼けたらしいと言われていますが。。。
このクスノキには、御神木と呼ばれるに相応しい逸話が残されているそうですよ



その昔、子どもを産んで お乳がでない母親が、洞穴のように穴が空いているクスノキの幹に
お米のとぎ汁を一升かけ、お祈りをすると お乳が出るようになったということから
その後、お乳がでない母親たちが多く参拝に訪れるようになったと言われています。
それが、安産祈願で訪れる参拝者が多い由縁カモ!?ということでした



長崎の神社には、必ず1本はこのような逸話を持った 巨大なクスノキが立っていますね・・・。