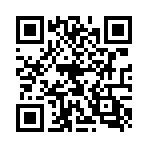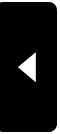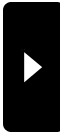2015年05月25日
信玄堤
水無川流域を目指して、まずは 「島原まゆやまロード」 を走ることに・・・。
眉山の西側を通り 「平成新山」 を間近に見上げるルートになります。
展望所などの駐車スペースもあって、火砕流や土石流が流れていった跡がよく見えました


中央にある山を中心にして二股に分かれ、手前の方は幅の広い谷のようになっていました。

白線のように見えているのは、以前あったダムの堤防のようですが。。。
全てスッポリと砂の中に埋もれていましたよ

もしかして、この砂の中には未確認のお宝たちが眠っていたのでしょうか!?
そして砂漠の中には、ポツポツとマリモのような苔玉???が転がっているような。。。

近くまでは立入り不可で行けなかったので、ズームで
 撮ってみると。。。
撮ってみると。。。
何でしょうかね?アカマツ?スギ?ゴールドクレスト・・・


ニュースで学生さんたちが、植樹されているのを昨年の秋だったかに見た記憶がありますが。。。
植物の種類は何だったか覚えてないのですが、間違いなくこれは植樹の証でしょうね



きっと年月をかけて、以前のように青々とした偉大な自然を築き上げていってくれる事でしょう!!
展望所から振り返って後ろを見ると、有明海の向うには阿蘇山でしょうか?
幽かに巨大な山並みが見えていましたよ・・・。

そしてこれは 水無川2号砂防えん提 だと思われます

このような えん提が有明海まで続いているのですが、これらは導流堤と呼ばれ発生した土石流を
導流堤の中だけに流れさせ、家や畑への被害を少なくするための堤防なんだそうです。
カタカナの 「ハ」 の字型に堤防を配置する事によって、 効率的に土砂の流出を食い止める方法から
武田信玄が その原型を編み出したと言われているそうですよ



ここから対岸にはマッポシ 【旧大野木場小学校被災校舎】 が見えていました。
校舎の右隣の建物は、雲仙普賢岳の監視を行う 「砂防みらい館」
平成3年、9月15日に大火砕流が発生し、この小学校は一夜にして焼失したそうです・・・。
何もかもなくなった・・・一夜にして 「死の町」
そのような見出しが 当時の新聞記事には書かれていました

自然災害のすざましさを継承する 大野木場被災遺構として、被災当時のまま保存されていて
外からは、その様子を見る事が出来ました・・・。
校庭にあった1本のイチョウの木も校舎と共に、火砕サージと呼ばれる大火砕流に伴う高温の
熱風によって焼かれてしまったものの、翌年には元気に芽を吹き 今は大きな木となって
生き続けていましたよ



この小学校の正面に、深江埋蔵文化財・噴火災害資料館というのがあって。。。
島原半島には 縄文時代から弥生時代へと移り変わる頃の 遺跡が多く存在しているらしく
「刻目突帯文(きざみめとったいもん)」 土器や、勾玉、打製石斧などがあるみたいです。
もちろん水無川流域の砂防工事に伴って出土した 遺物たちも展示されていたと思いますが
タイムオーバーで既に資料館は閉館しておりました


でも、現場を見たことで災害に対する関心度も少しは増した?ようにも感じるので。。。
貴重な体験が出来て良かったと思います


眉山の西側を通り 「平成新山」 を間近に見上げるルートになります。
展望所などの駐車スペースもあって、火砕流や土石流が流れていった跡がよく見えました



中央にある山を中心にして二股に分かれ、手前の方は幅の広い谷のようになっていました。
白線のように見えているのは、以前あったダムの堤防のようですが。。。
全てスッポリと砂の中に埋もれていましたよ


もしかして、この砂の中には未確認のお宝たちが眠っていたのでしょうか!?
そして砂漠の中には、ポツポツとマリモのような苔玉???が転がっているような。。。
近くまでは立入り不可で行けなかったので、ズームで

 撮ってみると。。。
撮ってみると。。。何でしょうかね?アカマツ?スギ?ゴールドクレスト・・・



ニュースで学生さんたちが、植樹されているのを昨年の秋だったかに見た記憶がありますが。。。
植物の種類は何だったか覚えてないのですが、間違いなくこれは植樹の証でしょうね



きっと年月をかけて、以前のように青々とした偉大な自然を築き上げていってくれる事でしょう!!
展望所から振り返って後ろを見ると、有明海の向うには阿蘇山でしょうか?
幽かに巨大な山並みが見えていましたよ・・・。
そしてこれは 水無川2号砂防えん提 だと思われます


このような えん提が有明海まで続いているのですが、これらは導流堤と呼ばれ発生した土石流を
導流堤の中だけに流れさせ、家や畑への被害を少なくするための堤防なんだそうです。
カタカナの 「ハ」 の字型に堤防を配置する事によって、 効率的に土砂の流出を食い止める方法から
武田信玄が その原型を編み出したと言われているそうですよ



ここから対岸にはマッポシ 【旧大野木場小学校被災校舎】 が見えていました。
校舎の右隣の建物は、雲仙普賢岳の監視を行う 「砂防みらい館」
平成3年、9月15日に大火砕流が発生し、この小学校は一夜にして焼失したそうです・・・。
何もかもなくなった・・・一夜にして 「死の町」
そのような見出しが 当時の新聞記事には書かれていました

自然災害のすざましさを継承する 大野木場被災遺構として、被災当時のまま保存されていて
外からは、その様子を見る事が出来ました・・・。
校庭にあった1本のイチョウの木も校舎と共に、火砕サージと呼ばれる大火砕流に伴う高温の
熱風によって焼かれてしまったものの、翌年には元気に芽を吹き 今は大きな木となって
生き続けていましたよ



この小学校の正面に、深江埋蔵文化財・噴火災害資料館というのがあって。。。
島原半島には 縄文時代から弥生時代へと移り変わる頃の 遺跡が多く存在しているらしく
「刻目突帯文(きざみめとったいもん)」 土器や、勾玉、打製石斧などがあるみたいです。
もちろん水無川流域の砂防工事に伴って出土した 遺物たちも展示されていたと思いますが
タイムオーバーで既に資料館は閉館しておりました



でも、現場を見たことで災害に対する関心度も少しは増した?ようにも感じるので。。。
貴重な体験が出来て良かったと思います



Posted by
おてきち
at
15:32
│
Comments(
2
)
│
風景
この記事へのコメント
火砕流跡の植林は、杉か檜だと思います。そこには、「シマバライチゴ」という日本では珍しいイチゴの木も生えていると聞いています。どんな味かな・・・・
Posted by
ハチ
at
2015年05月26日 08:43
ハチ様
シマバライチゴ???そのような珍しい果実があったのですか!!
今度、行く機会があれば探してみます(^-^)
ついつい珍しいッ☆と聞くと触手が伸びてイケマセンぜぃ~♪
シマバライチゴ???そのような珍しい果実があったのですか!!
今度、行く機会があれば探してみます(^-^)
ついつい珍しいッ☆と聞くと触手が伸びてイケマセンぜぃ~♪
Posted by
おてきち at
2015年05月27日 15:41
at
2015年05月27日 15:41
 at
2015年05月27日 15:41
at
2015年05月27日 15:41